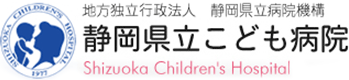心房中隔欠損症
心房中隔欠損症に対する外科治療
心房中隔欠損症に対する外科治療
心房中隔欠損(Atrial septal defect、ASD)は左右の心房の間を隔てる壁(心房中隔)の一部に穴が開いている先天性の心臓病です。心房間の交通は胎内では全員が存在します(卵円孔)が、出生後自然に閉鎖します。これと異なる穴がASDです。
ASDがあると左心房から動脈血が右心房に抜けるので、肺血流が増えることになります。抜ける量により症状が異なりますが、多くは症状が出ません。肺血流増加が続く場合、肺高血圧をきたす可能性はあります。
穴の大きさが5mm以下なら経過観察ですが、5-10mmだとカテーテル検査をし、穴を通る血液量に応じて治療が必要となります。10mm以上あり、心臓に負担が認められれば閉鎖の適応となります。方法は外科的に閉鎖する方法と、カテーテルで閉鎖する方法の二通りがあり、検査結果によってどちらが適切か判断します。カテーテルで閉鎖できない場合、もしくは希望される場合に手術での治療となります。
手術は、人工心肺を用いて、一時的に心臓を停止させた状態で心臓を開き、直接穴の大きさと場所を確認し、直接縫合かパッチ(主として自己心膜を使用します)で閉鎖します。心臓が再度動くような状態になってから人工心肺を離脱し、傷を閉じて終了します。
ただ、体格・年齢や心不全の程度により、アプローチが異なります。基本は胸骨正中切開で行います(「手術のアプローチ」のページをご覧ください)。
ASD閉鎖に十分な安全が確保できる場合、「胸骨部分切開」で行うことができます。これは、皮膚切開の長さを身長の7%程度歳、胸骨体のみ切開しアプローチする方法です。いわゆる間口が狭い手術方法になるので、多少やりにくさはありますが、美容の観点からご希望があれば取り組みます。安全が第一の手術ですので、非常に困難な場合は術中判断で胸骨正中切開に切り替えますが、現在までそのような症例はありません。
また、右開胸で手術を行うことも可能です。側胸を縦に切開する場合、右乳房の下面に沿って切開する場合があります。この場合、頸部や鼠径部の血管を併用し、さらに創部を小さくすることも考えています。
さらに、40kgを越えている場合は、内視鏡を併用した低侵襲手術もあります。ただし現時点では約2キロの距離にある県立総合病院で行っています(ASD以外の手術も含めて県立総合病院と合同で心臓手術を行うことが増えています)。
なるべく輸血を避け、血液製剤も使わない完全無輸血の方針も採っています。術後は集中治療室に入り、問題なく麻酔から覚めれば、人工呼吸器から離脱します。その後、1-2日で一般病棟へ移動します。およそ1週間の入院期間となります。必要に応じて術後の短期間のみ利尿剤や抗炎症剤を使用します。退院後は約1週間の自宅療養、一度外来診療を行い、社会復帰(学校、幼稚園など)可能となります。