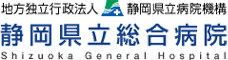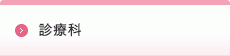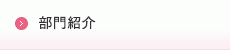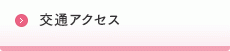微生物検査室で実施している検査
微生物検査室では患者さんから採取された材料(喀痰、尿、便、膿など)を培養し、どのような病原菌がいるかを見つけ出し、その菌にどんな薬剤が効くのかを調べることを主な仕事としています。
検査材料をスライドガラスに塗りつけ、染色し、どのような菌がいるか顕微鏡で観察します。
一般細菌染色
主にグラム染色で、ブドウ球菌、肺炎球菌、真菌(カビ)等は青色に、大腸菌、緑膿菌等は赤色に染まります。
抗酸菌染色
蛍光法(アクリステイン法)で、結核菌、非定型抗酸菌は光って見えチールネルゼン染色では赤色に染まります。
一般細菌染色
主にグラム染色で、ブドウ球菌、肺炎球菌、真菌(カビ)等は青色に、大腸菌、緑膿菌等は赤色に染まります。
抗酸菌染色
蛍光法(アクリステイン法)で、結核菌、非定型抗酸菌は光って見えチールネルゼン染色では赤色に染まります。
検査材料を数種類の培地に塗布(菌によっては特定の培地にしか発育しないものがある為)し、35゜Cフラン器で培養します。発育した菌が何と言う菌であるのか、菌集落(コロニー)形態、生化学性状などを調べて菌名を決定します。近年では菌の蛋白質などの分子の重さを量ることで菌名を同定する質量分析法もあります。
発育した病原菌が薬剤を含む培地に発育するかどうか、或いは、培地に薬剤を含んだディスクを置き菌の発育を阻止されるかどうかを調べ、その菌にどんな薬剤が効くのかを判定します。
培養をせずに、細菌及び培地に発育しないウイルスの存在を、検査材料から直接短時間で確認することができる検査です。
検査項目
|
|
遺伝子を用いた核酸増幅法
検査項目
| 結核菌群、マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC) レジオネラ、SARS-CoV-2、マイコプラズマ |
- 感染制御チーム院内ラウンド
- 薬剤感受性情報
- 細菌検出情報
- 耐性菌検出情報
- 抗菌薬適正使用支援チーム活動