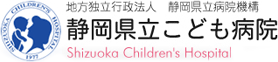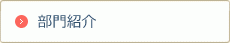無輸血手術について
どんな手術であろうとも、メスで切る以上出血はつきものですが、多くの心臓の手術では、「人工心肺」を使用します。人工心肺中は、血液が血管を出て、人工心肺や回路中を流れるので、容易に固まりやすい状態になります。血液が固まってしまう(血栓化)と、酸素ほかを運ぶという役目を果たさなくなり、各臓器への還流障害も引き起こします。そうならないよう、人工心肺の中で「全く血液が固まらない状態」(ヘパリンというお薬を大量に使用)を作り、手術を行います。つまり、手術中に“極めて出血が止まりにくい状況”が存在する中で行う手術になるため、人工心肺を使用しない手術と比較し、出血がはるかに多くなります。大量出血に対応する手段としては輸血があります。
このように、人工心肺を使用する心臓手術では輸血を必要とすることが多いのですが、当院では2002年以降、軽症例に対しては輸血・血液製剤を使用しない「完全無輸血手術」を導入しております。
ただし、新生児や、重症の心疾患患者さんなどでは、輸血は非常に有用であることに変わりはありません。無輸血手術が可能であればそれに越したことはありませんが、人間の体は極度の貧血状態では生命を維持できませんので、この貧血の限界を越えてまで無輸血手術を遂行するのはよくないばかりか、むしろ避けるべきと考えています。輸血をした場合、ウィルス感染などのリスクが完全には否定できませんが、ウィルス検査の制度は飛躍的に改善してきた昨今、「輸血によるリスク」と、「輸血をせずに極度の貧血状態に陥ることによるリスク」の両者を比較し、また疾患名だけでなく、年齢、体重、術前の状態、他の合併症の有無などの様々な因子を考慮し、必要時に適切に輸血を行うことが最も重要であると考えております。
「完全無輸血手術」の試みは、輸血ならびに献血由来薬剤の使用によるウィルス感染の可能性や、その他の合併症の防止を目的としています。このような危険性を少しでも減少させるため可能な限りの異物(自分のものではないもの)を使用しないことを目標に積極的に導入しております。完全無輸血手術の場合、血液製剤(輸血、献血由来の血漿分画製剤の全て)使用によるウィルス感染の可能性をほぼなくなります。したがって、術後の予防接種時期なども考慮に入れる必要がなくなります。
完全無輸血手術の対象は、以下の通りとなっています。
1. 体重12kg以上の単独の心房中隔欠損症、心室中隔欠損症患者
2. 初回手術
3. 止血、凝固異常などの血液疾患のない患者体重15kg以上の患者
どんな手術であろうとも、メスで切る以上出血はつきものですが、多くの心臓の手術では、「人工心肺」を使用します。人工心肺中は、血液が血管を出て、人工心肺や回路中を流れるので、容易に固まりやすい状態になります。血液が固まってしまう(血栓化)と、酸素ほかを運ぶという役目を果たさなくなり、各臓器への還流障害も引き起こします。そうならないよう、人工心肺の中で「全く血液が固まらない状態」(ヘパリンというお薬を大量に使用)を作り、手術を行います。つまり、手術中に“極めて出血が止まりにくい状況”が存在する中で行う手術になるため、人工心肺を使用しない手術と比較し、出血がはるかに多くなります。大量出血に対応する手段としては輸血があります。
このように、人工心肺を使用する心臓手術では輸血を必要とすることが多いのですが、当院では2002年以降、軽症例に対しては輸血・血液製剤を使用しない「完全無輸血手術」を導入しております。
ただし、新生児や、重症の心疾患患者さんなどでは、輸血は非常に有用であることに変わりはありません。無輸血手術が可能であればそれに越したことはありませんが、人間の体は極度の貧血状態では生命を維持できませんので、この貧血の限界を越えてまで無輸血手術を遂行するのはよくないばかりか、むしろ避けるべきと考えています。輸血をした場合、ウィルス感染などのリスクが完全には否定できませんが、ウィルス検査の制度は飛躍的に改善してきた昨今、「輸血によるリスク」と、「輸血をせずに極度の貧血状態に陥ることによるリスク」の両者を比較し、また疾患名だけでなく、年齢、体重、術前の状態、他の合併症の有無などの様々な因子を考慮し、必要時に適切に輸血を行うことが最も重要であると考えております。
「完全無輸血手術」の試みは、輸血ならびに献血由来薬剤の使用によるウィルス感染の可能性や、その他の合併症の防止を目的としています。このような危険性を少しでも減少させるため可能な限りの異物(自分のものではないもの)を使用しないことを目標に積極的に導入しております。完全無輸血手術の場合、血液製剤(輸血、献血由来の血漿分画製剤の全て)使用によるウィルス感染の可能性をほぼなくなります。したがって、術後の予防接種時期なども考慮に入れる必要がなくなります。
完全無輸血手術の対象は、以下の通りとなっています。
1. 体重12kg以上の単独の心房中隔欠損症、心室中隔欠損症患者
2. 初回手術
3. 止血、凝固異常などの血液疾患のない患者体重15kg以上の患者